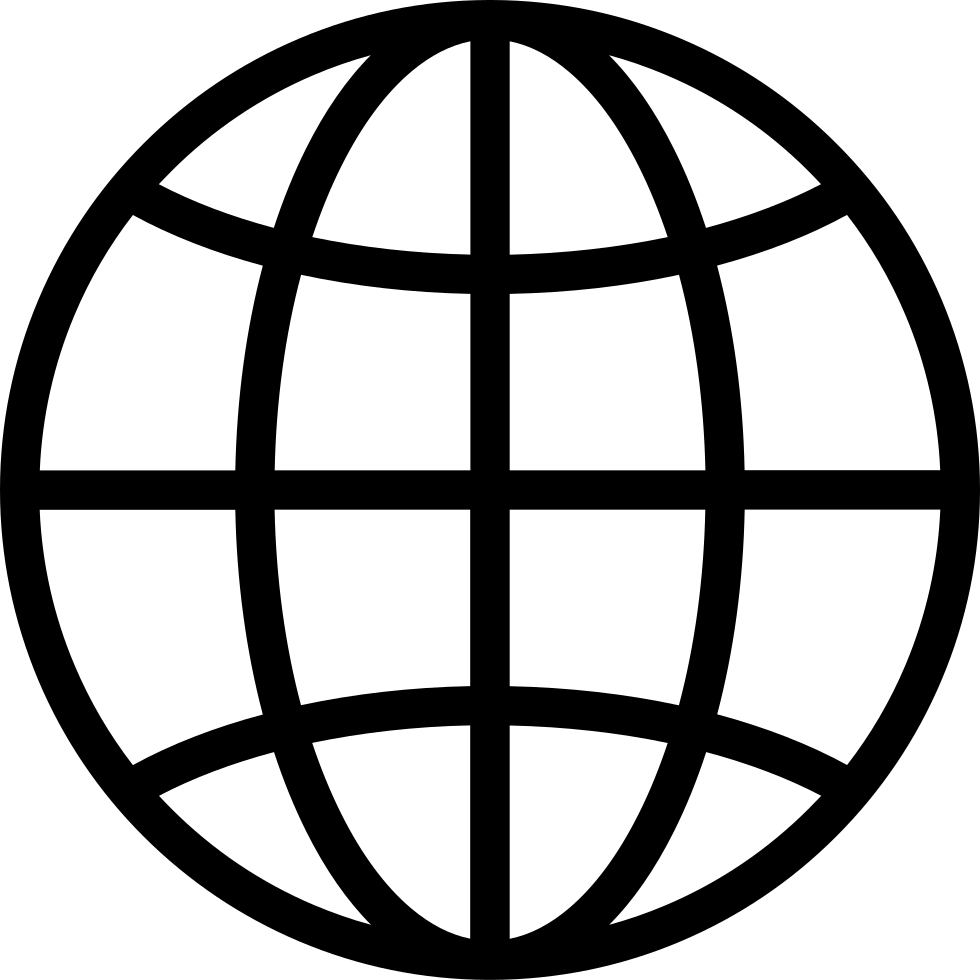Radio Dialogue 第1回
Manage episode 269745556 series 1025539
Contenuto fornito da Project Dialogue. Tutti i contenuti dei podcast, inclusi episodi, grafica e descrizioni dei podcast, vengono caricati e forniti direttamente da Project Dialogue o dal partner della piattaforma podcast. Se ritieni che qualcuno stia utilizzando la tua opera protetta da copyright senza la tua autorizzazione, puoi seguire la procedura descritta qui https://it.player.fm/legal.

Radio Dialogue第1回を配信します。
収録は10月3日(土)の午前0:00から開始し、午前3:00頃終了しました。
「わからない」をテーマに2人の話者が話題を持ち寄って対談し、フリートークののち最近読んだ本について話しました。番組に関する詳細および解説は記事の下部をご覧ください。
第2回の配信は10月中旬を予定しています。
Radio Dialogueではリスナーの皆さんのコメントを募集しています。「わからない」、あるいは「わかる」についてがんがんご意見・感想・その他をお寄せください。Twitterのハッシュタグは
○2015年10月15日追記○
Radio Dialogue 第1回の全編をYouTubeにて公開中です↓
Radio Dialogue 第1回(クリックするとリンクへ飛びます)
2時間程度の長さ、聞き逃しても悔しくない内容――作業用BGMに最適です。
ぜひご視聴ください。
話者:
GARIO:大衆小説家。感情を忘れてきた。
カノウソウスケ:退廃音楽家。よく笑う。
番組の進行は以下の通り:
・趣旨説明
・先攻:GARIO「共感性について」
・後攻:カノウソウスケ「医者のかかりかたがわからない」
・フリートーク
・読書コーナー:『姉飼』『機械より人間らしくなれるか?』


Vol.1 OP-Section A
このブラウザでは再生できません。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
Keywords:
共感性
援助行動
サイコパス
生まれ持った性質
Vol.2 Section B
このブラウザでは再生できません。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
Keywords:
受診
医療
コミュニケーション
脳
主観性・客観性
Vol.3 Free Session
このブラウザでは再生できません。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
Keywords:
世界観
味覚
笑い
感覚
食べ物
おいしさ
発酵と腐敗
”生(なま)”という概念
Vol.4 Book Session
このブラウザでは再生できません。
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら
Keywords:
ホラー
恐怖
人工知能(AI)
チューリング・テスト
ディープラーニング
技術的特異点(シンギュラリティ)
ロボティクス
↓↓トークの解説を読む↓↓
Vol.1 OP-Section A
00:46 話者(わしゃ):話す人のこと。
02:20 収録は日本時間で2015年10月3日AM0:00から行なわれた。
04:18 筆名(ひつめい):ペンネームのこと。
04:42 P名(ぴーめい):かつてニコニコ動画の音声合成界隈では、視聴者が動画投稿者にP名(プロデューサー名)として愛称をつける風習があった。
06:56 メトリック(metric):測度、尺度に関すること。
07:20 先攻(せんこう) 野球など攻撃と防御とを交互に行うスポーツの試合で、攻撃の順番が先であること。
08:33 『社会心理学キーワード』p148:共感性について詳しく記述されているものの、共感性の定義ははっきり書かれていない。

社会心理学キーワード (有斐閣双書―KEYWORD SERIES) -
09:02 共感 - Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%B1%E6%84%9F
12:28 「コミュ力(こみゅりょく)」:コミュニケーション能力の略。コミュニズム力ではない。
14:02 援助行動(えんじょこうどう):他人を助ける行動。さまざまな分野で研究が行われている。
17:18 「メタ」共感:メタ(meta-)は「より上位の」を意味する接頭辞。例えばメタ記憶といえば「記憶についての記憶」ということになる。ここでは共感に対するメタ認知に近いかもしれない。
18:14 「合理的なプロセス」:人間の情報処理には思考による冷静で計算的な処理(アルゴリズム)とそうではない簡便法的な処理(ヒューリスティクス)があることが経験的に知られている。ここでは前者に近い処理をしているのか、という程度の意味。
18:17 セカンドベスト(second-best):次善の。最善(ファーストベスト)ではないがそれに次ぐ手であるということ。
19:45 「原始人」:大昔、原始的な社会で暮らしていた人間を指している。人間より前に存在したヒト科動物を指しているわけではない。
20:22 村八分:みんなから仲間はずれにされること。現代ならともかく、手と手を取り合って暮らしていた原始的社会では、仲間はずれは命にかかわるくらいの仕打ちだったろう。
22:40 ここで笑ったのは共通の知り合いを想像したため。
24:33 セレクション(selection):ここではnatural selection(自然淘汰)のこと。統計学の文脈では特定の属性を持った標本が集まってしまい、集団全体が偏ってしまうセレクションバイアス(選択バイアス)というものもある。どちらも、特定の性質を持つ個体が選択される(それ以外が淘汰される)という含意がある。
25:21 サイコパス(psychopath):精神病質者。反社会的人格を有すると言われている。サイコパス傾向にはなんらかの生得的・器質的な基盤があるのではないか、すなわちサイコパスはサイコパスたる何かを生まれ持っているのではないかと考えられている。
25:30 「アニメで~」: PSYCHO-PASS - Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/PSYCHO-PASS
25:50 元名大女子学生の精神鑑定終了 名古屋家裁 :日本経済新聞 | http://www.nikkei.com/article/DGXLASFD28H2K_R30C15A8CN8000/
26:04 DSM:Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(精神障害の診断と統計マニュアル)。アメリカ精神医学会によって出版されている精神障害の診断に関する手引き。現在第五版(DSM-5)が最新。
27:38 責任能力:刑法上は犯罪成立の必要条件として、構成要件該当性(法律上定められている犯罪の類型に適合するか)・違法性、そして有責性が求められる。そのため違法な行為であっても、行為者が責任能力のない場合は処罰されないことがある。
27:58 減軽(げんけい):犯罪の成立が認められた場合にその情状を酌量して処罰を軽くすること。
28:11 吉良吉影(きらよしかげ):荒木飛呂彦『ジョジョの奇妙な冒険』第四部に登場するキャラクター。触れたものを爆弾に変える能力を持つスタンド「キラー・クイーン」を操る。生まれつきの
30:19 神経犯罪学(しんけいはんざいがく):犯罪といった反社会的行動の神経的基盤を研究する学問。同名の書が出版されている。
31:15 マイノリティ・リポート(Minority Report):スピルバーグ監督によるSF映画。フィリップ・K・ディックの同名小説(The Minority Report)が原作。予知能力によって犯罪者が未然に捕えられる社会を描く。
32:04 状況証拠(じょうきょうしょうこ):犯罪事実を間接的に証明する証拠のこと。
32:52 ディストピア(dystopia):理想郷(ユートピア)の正反対の社会。はじめからディストピアを作ろうとする人はほとんどおらず、たいていユートピアを作ろうとしてどこかで道を誤るものだ。
Vol.2 Section B
00:01 後攻(こうこう):先攻に対して、攻める順番が後であること。
02:02 「赤い背景の~」:レッド・グリーンテストというらしい。
04:27 「しゅうそ」:愁訴。
11:01 ランドルト環:視力検査に使われる切れ目の入ったリングのこと。
12:06 「俺の目を盗んだな」:アニメ『攻殻機動隊SAC』の登場人物、バトーの台詞(正しくは「俺の目を盗みやがったな」)。
12:31 「のうりょう」:脳梁 - Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B3%E6%A2%81
12:46 「自分ではわからないのにわかっている」:知覚的には視覚を喪失した人が主観的な「見え」の感覚を持たないのに視覚刺激に反応する「盲視」という現象が知られている。
12:50 てんかんの治療などの理由で脳梁を切断された、すなわち右脳と左脳が分離された脳の状態を「分離脳」と言う。分離脳患者に起きる奇妙な現象についてはWikipediaの「分離脳」の項にて。→https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%86%E9%9B%A2%E8%84%B3
15:15 モスキート音:加齢による可聴域の減少のため、年齢によって聞こえるか聞こえないかが変わる超高音域の音。不快に感じられるとされる。「若者にしか聞こえない音」と形容される。ちなみに「モスキート」は商品名。
18:13 「70億人くらい~」:世界人口は2011年に70億を突破。
18:52 共同注視(きょうどうちゅうし):相手と視線を共有し、同じ事物に注意を向けること。英語ではjoint attention。
Vol.3 Free Session
00:44 「ハウル~」:ちょうど10月2日の金曜ロードショーは「ハウルの動く城」であった。
02:23 「~のかしら」:「~のか知らん」の短縮形。「ドラえもん」ののび太君などがよく使う。
04:54 加齢変化。年齢を経たことで体質とか嗜好が変化すること。カレー変化ではない。
05:42 腐敗という現象のうち、人間に都合いいものを発酵と呼ぶ。
06:56 「水銀」:日本生協連のホームページによると、どうやらサンマはメチル水銀の危険性の低い魚の部類になるらしいので、水銀うんぬんは適切な理由でないようだ。なぜサンマの内臓を食べるのかについては以下の記事を参照のこと。→なぜ秋刀魚の内臓は食べられるの? | http://homepage2.nifty.com/osiete/s671.htm
08:22 ×「他のサンマのわた」→○「他の魚のわた」
09:49 「この料理を作ったのは誰だ」:料理漫画『美味しんぼ』4巻における美食家・海原雄山の台詞。正しくは「このあらいを作ったのは誰だあっ!!」
11:00 トライアル(trial):試行。
11:37 「ちょうそう」:鳥葬。チベット仏教やゾロアスター教における葬儀の仕方。死体を荒地に設置された鳥葬台に置き、ハゲワシなどに食べさせるというもの。ちなみに鳥葬で画像検索するとショッキングな写真が出るので注意。
12:14 「どのお笑い芸人が面白いか」:どうやら関西出身のGARIOにとっては笑いは身体的感覚に近いようである。
16:20 「リコリッシュというか」:以下を参照のこと。→リコリス菓子 - Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%82%B3%E3%83%AA%E3%82%B9%E8%8F%93%E5%AD%90
16:24 サルミアッキ:塩化アンモニウムとリコリスでできたお菓子。世界一まずい飴などと言われるが、フィンランドなどの北欧の国々では愛されているらしい。キャンディが有名だが、チョコレートやアイスクリームと形態はさまざま。GARIOはカノウがおみやげとして買ってきたのを試食したことがある。
19:11 シュールストレミング:スウェーデンの特産の発酵食品。世界一臭い食べ物と呼ばれる。詳しくは以下のwikipediaの記事を参照→ https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%9F%E3%83%B3%E3%82%B0
19:28 「川かどっかで~」:日本でシュールストレミングの輸入を取り扱う川口貿易のページでは「(1)必ず屋外で、できればビニール袋(ゴミ袋)の中で開缶してください。醗酵が進んでいると汁が噴き出します。 周囲や風下に人がいないことを充分に確認して缶を開けてください。(2)衣服や室内に汁が飛ばないようにご注意下さい。※汁がついた服は洗濯しても臭いやシミが取れなくなります。あきらめましょう。」との注意があったが、川という記載はなかった。話者の誤認か (シュールストレミングを食べるWeb記事では河川敷で開封していることが多い)。
20:20 スペクトラム(spectrum):連続体。スペクトル。ここでは食品の腐敗の過程は連続的であり、腐る瞬間を特定することはできない、という程度の意味。
21:33 生卵の賞味期限:日本養鶏協会による生卵の賞味期限の説明→ 日本養鶏協会 | http://www.jpa.or.jp/chishiki/anshin/01.html
23:03 アニサキス: 魚介類から感染する寄生虫。線虫の仲間。寄生を防ぐためには60℃で1分以上の加熱、あるいは長時間の冷凍が必要。
23:24 「サケは川魚か」:どうやらサケは回遊魚に分類されるらしい。ちなみに身に色がついているが白身魚である。
23:36 ルイベ:冷凍保存した魚を凍ったまま刺身にして味わう魚料理。アイヌ語で「融けた食べ物」の意。
23:48 北大路魯山人:日本の芸術家。美食家として知られる。
24:14 「死因って書いてある」: 検索バーに「北大路魯山人」と入力したら単語候補として出てきた。
24:30 見たページはこちら:北大路魯山人の死因|人間ドック専門クリニック「わかすぎファミリークリニック」 | http://ameblo.jp/e-dock/entry-11627819877.html
24:34 「かんきゅうちゅう」:肝吸虫。寄生虫の一種。
25:41 「寄生虫はヤバいですよ」:そういえばこの春、カノウは東京は目黒の寄生虫館を見学してきたのだった。
26:25 これである→ http://donnk.com/doku/
26:43 レバー問題:食品衛生法に基づき、2012年7月1日より飲食店や販売業者が牛のレバーを提供する行為が禁止された。また、2015年6月12日より豚レバーについても同様に禁止された。
→厚生労働省「牛レバーを生食するのは、やめましょう」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syouhisya/110720/
「豚のお肉や内臓を生食するのは、やめましょう」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/syouhisya/121004/
27:18 「評判があがる、みたいな」:一見生存の可能性を下げるような形質が進化することの説明のひとつとして「ハンディキャップ理論」がある。たとえば、クジャクのオスが持つきれいな尾羽は運動の妨げになるが、一方でそんなものをぶら下げてても生きていられるほど優れた肉体を持つのだというシグナルにもなる。
28:59 余談だが、今でも老人ホームなどでは生野菜を洗剤で洗ってから提供している。
29:01 台所用洗剤が野菜の回虫卵の保有率の低下や農薬除去に効果を発揮したという記述がある。→日本石鹸洗剤工業会 台所用洗剤の役割と技術の変遷 | http://jsda.org/w/01_katud/a_seminar09.html
29:18 「サナダムシですね、特に」:得意げにいっているが、回虫や蟯虫も含まれるので必ずしも適切ではない。
35:41 『セクシィ・ギャルの大研究』:著者は上野千鶴子。世の中のエロティックな広告をフェミニスト的観点から分析したもの。話題には挙げたものの、詳細な内容を忘れてしまっている。読み直すことにする。

セクシィ・ギャルの大研究―女の読み方・読まれ方・読ませ方 (岩波現代文庫) -
Vol.4 Book Session-ED
00:38 「あねかい」:「姉飼」。遠藤徹の小説。第10回日本ホラー小説大賞受賞作。
02:51 大槻ケンヂ:日本のミュージシャン、作家。サブカルチャーに強い。
06:02 『機械より人間らしくなれるか?』:著者はブライアン・クリスチャン。
06:11 チューリング・テスト:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%83%86%E3%82%B9%E3%83%88
06:14 チューリング(Aran Turing, 1912-1954):イギリスの数学者・コンピュータ科学者。計算可能性理論をはじめとするコンピュータ科学への貢献や、暗号解読で知られる。同性愛の罪で逮捕され、後に青酸中毒にて死去。2009年にイギリス政府が公式に謝罪し、名誉回復がなされた。
07:03 「チューリングテストの大会がアメリカで」:ブライアン・クリスチャンが参加した2009年の大会はイギリスのブライトンで開かれたので正確ではない。
08:44 ディープラーニング(deep learning):深層学習。多層構造を持つニューラルネット。ニューラルネットは、機械学習の方式の一つで、神経細胞を模したノード(人工ニューロン)の層からなる。画像認識や音声認識にすぐれる。
08:49 ディープドリーム(deep dream):Googleが発表した深層学習アルゴリズム。予め学習した画像をもとに、入力された画像に処理を施すことでサイケデリックな画像を出力する。
09:19 シンギュラリティ(singularity):技術的特異点(テクノロジカル・シンギュラリティ)のこと。現在の人類による科学技術の進歩の限界点。この限界点以降、科学技術の進歩は「強い人工知能」や知能をブーストされた人類に取って代わられ、現在の人類の理解できない領域に至るとされる。
10:03 道具主義:科学哲学の用語。ここでは、チューリングテストが「AIが本質的な人間性を持つかどうか」より「うまく人間を装うことができるかどうか」を判定するためのテストになっているのではないかという疑問を呈するために用いている。
11:05 パラダイム(paradigm):科学哲学の用語。非常に複雑な概念だが、誤解を恐れず言えば、ある科学分野において現在支配的な考え方のこと。
11:08 機械学習:人間が行っている学習と同様のことをコンピュータで実現しようとする技術のこと。
12:26 「鳥とかの種族の推定は~」:画像認識でそういう例があったという記事を見た気がするが発見できず。
14:28 「いるんです、そういう人がね」:もちろん違う人も沢山いるのでよろしく。
16:26 ロボティクス:ロボット工学のこと。大阪大学の創発ロボティクス研究室では、身体性と世界との相互作用を軸に人間の認知発達の理解を目指しているとのこと。→Asada Laboratory | Emergent Robotics Laboratory | http://www.er.ams.eng.osaka-u.ac.jp/asadalab/?page_id=36
16:57 身体性:さまざまな分野で独自の定義がある用語。Wikipediaの「身体性」の項の「認知科学・人工知能における身体性」を参照。→https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BA%AB%E4%BD%93%E6%80%A7
21:19 なおアイザック・アシモフが提唱した「フランケンシュタイン・コンプレックス」という概念がある。→フランケンシュタイン・コンプレックス - Wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
23:59 ラダイト運動:1811年から1817年頃、産業革命により機械が普及したことで失業を恐れた労働者が起こした機械破壊運動。→https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%83%83%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%88%E9%81%8B%E5%8B%95
26:35 エンディング曲"Ending Love Song"。編集のかたわらカノウソウスケが作詞・作曲した。

6 episodi